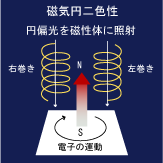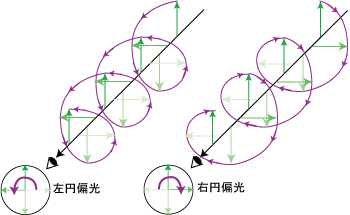| >研究内容>MCD |

可視紫外巨大光電子磁気円二色性を発見
|
|
可視紫外巨大光電子磁気円二色性を発見 |
|
|||||||||
| この研究を行った動機は何ですか? ナノスケールの空間分解能をもつ磁性を見る顕微鏡は、第三世代シンクロトロン放射光源が必要で、我が国ではSpring-8でのみ実験が可能です。 ところがSpring-8ではまだ時間分解測定が全くなされていません。エネルギーの低い軟X線領域の新たな放射光施設建設は東京大学を中心に大変な努力がなされましたが、 結局我が国の経済情勢が思わしくなく断念されてしまいました。 もともと横山Gは放射光を利用した研究を推進してきましたが、何とか放射光を利用せずに測定できないかという助手の中川の強い意志が今回の発見につながったと思います。 この研究の重要さや新しいところを専門外の人に説明してくださいますか? この研究は一言でいうと「紫外光電子磁気円二色性の増大効果の発見」になります。 言葉の説明は後にも述べますが、これまで紫外光を用いても十分なコントラストの光電子磁気円二色性は望めず、X線を用いるべきという先入観と実験事実がありました。 仕事関数ぎりぎりのエネルギーで紫外光の波長を変えた実験がほとんど行われていなかったことが今回の発見がこれまでなされなかった理由です。 エネルギーが十分大きい場合と比べて2-3桁コントラストが増加したことは、今後の計測に質的な変革をもたらすものです。 今後この研究はどのように発展すると考えられますか? 現在は第3世代放射光施設という巨大設備を使って空間分解能が数10nm、時間分解能が100psですが、この発見に基づいた紫外磁気円二色性光電子顕微鏡が完成すれば、 実験室内で空間分解能が数10nm(同じ性能の顕微鏡を用いると紫外光の方が空間分解能に勝ります)、時間分解能が10-100fs (フェムト秒、1fsは千兆分の1秒)の顕微鏡ができることになります。 特に時間分解能の千倍以上の向上は目を見張るものがあり、超高速スピンダイナミクス追跡(1ps以下の非常に速い時間で磁石=スピンの向きがどう変わっていくかの追跡)実験が可能となります。 |
|
| 論文名 "Magnetic Circular Dichroism near the Fermi Level" Takeshi Nakagawa and Toshihiko Yokoyama, Phys. Rev. Lett. 96, 237402 (2006). |